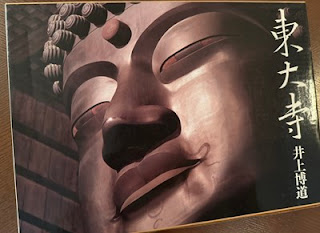三浦雅之さんの新著「奈良のタカラモノ」が届きました。
目次を開いて目にした内容の一つ一つに、三浦さんが大切にしてこられた大和野菜への愛が溢れているのがわかりました。
第一章は「はじまりの奈良を巡る旅」をテーマに
奈良発祥の歴史文化、そして奈良で生み出されたモノ・コトを紹介。
奈良で始まった文化や工芸もですが、何より現代の日本食へと続く「はじまりの食」の豊富なこと!
日本全国で生産されている西瓜種子の約9割が「大和西瓜」をベースに開発されているとか、現代の食文化を豊かにしている「苺の促成栽培」技術も奈良発祥だとか。
「はじまりの食」の紹介だけでなく、奈良の「食文化」を担う第一人者にインタビューをして専門的な知見をまとめてご紹介されているのも、この本の魅力です。
そして時々挟まれる「特集」のページも勉強になります。
「奈良の郷土食」には、まだ食べたことのないものもあって食欲がそそられます(笑)
「苺の促成栽培」と「大和西瓜」のページは、読んでいて胸アツ。
第二章は「 奈良のタカラモノ~家族野菜を未来につなぐ旅」
奈良県の伝統野菜について、まず①「多種多様な野菜はどこで誕生して日本に伝来したのか」から始まり、②「奈良県の野菜に対するブランド化の取り組みの歴史」③「奈良県のブランド野菜である大和野菜」について、かなり詳しく知ることができます。
京都の京野菜に習いブランド化を目的に、平成元年から伝統野菜の選定を行い産地化を支援して「大和伝統野菜」が生まれますが、この取り組みは十分な成果を得ることなく、その後平成17年より3つの認定基準を決めて14品目の「大和野菜」が誕生。
現在は25品目が「大和野菜」の認定を受け、その中の20品目が「大和伝統野菜」として数えられています。
そんな大和野菜をひとつひとつ丁寧に取り上げて紹介されているのが第二章です。
目次を見ても、紹介されている野菜の種類の多さに驚きますし、どの野菜にも育てている農家さんが紹介されています。
三浦さんご自身が28年間に渡って、奈良県内各地に埋もれていた在来種の調査・発掘と保存を続けてこられた中で育まれた関係が伝わってきます。
また、第二章のコラムでは、大和野菜が食べられるレストランが7軒紹介されていますので、奈良旅でのお食事処として参考にされてもと思います。
この章の中に書いてあった、「田からの賜りもの」でもある伝統野菜を「タカラモノ」と話していたというエピソードに心惹かれました。(三浦さんもその言葉からインスピレーションを得て本のタイトルにされたそうです)
大和野菜は『売る野菜=お金のなる野菜』ではなく、『自ら作って自ら食べる野菜』であり、美味しくて作りやすいからこの野菜を作ってきたと、三浦さんの聞き取り調査で答えて下さる方が多いそうです。
「大和の伝統野菜」が作りやすいというのはその土地の気候風土に適しているから、食べる人の顔を思い浮かべて育てられてきた「家族野菜」とも表現できるとおっしゃってます。
第三章では「懐かしくて新しい未来の暮らし」をテーマに、家族野菜を未来につなぐこと、三浦さんご自身のこと、山羊との暮らし、奥様の陽子さん、三浦さんと交流のある方々、2022年に奈良で開催されたガストロノミーツーリズムでの基調講演★、七つの風と七つの自給率について等々、未来へのビジョンやたくさんのことが詰まっています。
この中に書いてあった三浦さんの言葉ですが「調査をしている中で伝統野菜が多く残っている地域には比例して伝統芸能やその土地固有の生き物、また集落機能が残っていたことに興味をひかれました。」というところに、奈良という土地柄が表われているように思いました。
三浦さんは、地域のことを足元から学び生業に生かすコミュニティとして、「はじまりの奈良フォーラム」そして「はじまりのムラcotocoto」を立ち上げて、奈良にご縁深い方々とともに勉強会を通して知見の共有を行っていらっしゃいます。
有難いことにその末席に加えていただき
「奈良の宝物な人々」の中に私も登場させていただきました。
こちらに書いてあるように、より良い未来に向けて、私の場合は奈良を訪れる人に奈良の魅力をお伝えしていきたいと、これからも自分のライフワークに取り組んでいこうと思いました。
三浦さん、陽子さん、素晴らしい「奈良のタカラモノ」を世に出して下さってありがとうございます。
そして、あらためて発刊おめでとうございます。
「奈良のタカラモノ」はAmazonで取り扱っているほか
本日より啓林堂書店での取り扱いが始まっています。
出版社の京阪奈情報教育出版のオンラインショップでも購入可能です。
https://narahon.stores.jp/items/67489527401c3115ff4f846d
大和野菜を通して、歴史や文化だけでない奈良の魅力を知ることができますので、是非どうぞ手に取ってご覧くださいませ。
尚、ブログ内の画像はすべて三浦さんよりご提供いただき、紙面全面掲載についても許可を得ています。